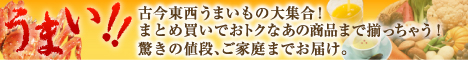
防犯や防災時に役立グッズが多数 「備えて安心グッズのお店」
お得なわけあり商品を多数取り揃え 「訳ありお得館」
厳選デジタルグッズのお店 「おもしろデジモノのデジモノ屋」
厳選食品お取り寄せのお店 「まんぷく屋」
美と健康を考えるお店 「La beaut」
ラズベリーパイ注文 ― 2012年09月12日 16時47分14秒
Raspberry Pi と言うのをご存知ですか?
デザートではなくて、Linuxが動くボードPCです。
以前から気にはなっていましたが、なんといっても
低価格なので、今回注文してみました。
もっとも、現状では届くまでに11週間かかるということで、
手に入るのは年末になりそうです。
これまでにも、小型のLinuxマシンが出ていましたが、
安くても2~3万円していたので、10分の一で購入できることを考えると、
本当に安いですよね!
実は今まで自宅でサーバーを立てようと思ったことがあるのですが、
夏場の暑さで断念していました。
OpenBlocksという製品であれば真夏の我が家においても
動作できそうだったのですが、Raspberry Pi であれば壊れても3千円程度なので、
年末に届いていろいろ試した後に夏が来て、真夏の高温に耐えられずに壊れても、
許せる範囲かなぁと思っております。
届きましたら、またレポートします。
デザートではなくて、Linuxが動くボードPCです。
以前から気にはなっていましたが、なんといっても
低価格なので、今回注文してみました。
もっとも、現状では届くまでに11週間かかるということで、
手に入るのは年末になりそうです。
これまでにも、小型のLinuxマシンが出ていましたが、
安くても2~3万円していたので、10分の一で購入できることを考えると、
本当に安いですよね!
実は今まで自宅でサーバーを立てようと思ったことがあるのですが、
夏場の暑さで断念していました。
OpenBlocksという製品であれば真夏の我が家においても
動作できそうだったのですが、Raspberry Pi であれば壊れても3千円程度なので、
年末に届いていろいろ試した後に夏が来て、真夏の高温に耐えられずに壊れても、
許せる範囲かなぁと思っております。
届きましたら、またレポートします。
USB-Linux作成 ― 2011年05月19日 16時33分17秒
前職の学校では、Linuxを使う機会が少なく縁遠い存在になっていたのですが、
今の職場では、多少使うようになっています。
一番よく使うのは、PHPのテストサーバーとしての利用です。
また使い始めたLinuxをもう少し活用しようと、今回USBにインストールして、
緊急時などに使えるようにしたいと思います。
USBにインストールするのは、Fedora14にしました。
SUSEなども候補として考えてみたのですが、
やはり慣れているRedhat系のディストリビューションが良いと思い、
Fedoraにしました。
ネットなどで調べてみると、USBへも今では簡単にインストールができるようです。
というのも、「Fedora LiveUSB Creator」というツールが出ていて、
それを使えば、簡単にUSBにインストールできるようなのです。
さっそく、「Fedora LiveUSB Creator」をダウンロードして、
インストールしました。
操作はいたって簡単です。
「TargetDevice」をUSBメモリーにする!
「Persistent Storage」を必要に応じて調整する。
「Create Live USB」ボタンをクリックする!
以上でインストール処理がはじまります。
ただし、LiveCDがある場合は「Browse」ボタンから選択してからインストールした方が良いです。
でないと、LiveCDをダウンロードするので、時間がかかります。
「Persistent Storage」っていうのが何のためのものなのか、
今一つわからなかったので、とりあえず容量の半分くらいにしておきました。
USBメモリー側にも注意が必要で、FAT32でフォーマットされている領域にインストールを
行うようで、たまたまNTFSに変更していた私のUSBは最初蹴られてしまいました。
あとはインストールされるのを待つだけです。
結構時間がかかりましたが、無事インストールが済み、さっそく起動させてみました。
USBの速度の問題でしょうが、正直起動には時間がかかります。
最近のUSBは転送速度も上がっているのでしょうが、
私の持っているのはちょっと古めなので、これは仕方ないですね!
無事立ち上がり、使えるようになりました。
Linuxを勉強し始めたころに比べると、本当に簡単になったもんです。
今の職場では、多少使うようになっています。
一番よく使うのは、PHPのテストサーバーとしての利用です。
また使い始めたLinuxをもう少し活用しようと、今回USBにインストールして、
緊急時などに使えるようにしたいと思います。
USBにインストールするのは、Fedora14にしました。
SUSEなども候補として考えてみたのですが、
やはり慣れているRedhat系のディストリビューションが良いと思い、
Fedoraにしました。
ネットなどで調べてみると、USBへも今では簡単にインストールができるようです。
というのも、「Fedora LiveUSB Creator」というツールが出ていて、
それを使えば、簡単にUSBにインストールできるようなのです。
さっそく、「Fedora LiveUSB Creator」をダウンロードして、
インストールしました。
操作はいたって簡単です。
「TargetDevice」をUSBメモリーにする!
「Persistent Storage」を必要に応じて調整する。
「Create Live USB」ボタンをクリックする!
以上でインストール処理がはじまります。
ただし、LiveCDがある場合は「Browse」ボタンから選択してからインストールした方が良いです。
でないと、LiveCDをダウンロードするので、時間がかかります。
「Persistent Storage」っていうのが何のためのものなのか、
今一つわからなかったので、とりあえず容量の半分くらいにしておきました。
USBメモリー側にも注意が必要で、FAT32でフォーマットされている領域にインストールを
行うようで、たまたまNTFSに変更していた私のUSBは最初蹴られてしまいました。
あとはインストールされるのを待つだけです。
結構時間がかかりましたが、無事インストールが済み、さっそく起動させてみました。
USBの速度の問題でしょうが、正直起動には時間がかかります。
最近のUSBは転送速度も上がっているのでしょうが、
私の持っているのはちょっと古めなので、これは仕方ないですね!
無事立ち上がり、使えるようになりました。
Linuxを勉強し始めたころに比べると、本当に簡単になったもんです。
VirtualPCにLinuxをインストール2 ― 2010年02月03日 12時52分15秒
CentOSはテキストモードであれば、問題なく動くのですが、Xを立ち上げると画面が正常に表示されなかったので、他のLinuxも試してみました。
今回試してみたのはSUSEとubuntuです。
まずSUSEですが、インストール作業自体は、グラフィカルで実行できるのですが、インストールが終わっていざ起動となると、CentOS同様画面が正常に表示されませんでした。
やっぱりグラフィックに関してはうまくいかないようです。
続けて、ubuntuをインストール!
こちらもインストール作業は問題なく完了しました。
不安を感じながらも起動させると、ubuntuは普通に起動しています。
ネットワークの設定などを行い、ネット接続もできています。
Linuxの環境をどうするか考えた結果、CentOSをテキストモードでサーバーとして使い、ubuntuを開発環境として使うという方向で使っていきたいと思います。
VMWareServerのほうが機能としてはよさそうな気もするのですが、ある程度使ってみて最終的な判断をしたいと思います。
今回試してみたのはSUSEとubuntuです。
まずSUSEですが、インストール作業自体は、グラフィカルで実行できるのですが、インストールが終わっていざ起動となると、CentOS同様画面が正常に表示されませんでした。
やっぱりグラフィックに関してはうまくいかないようです。
続けて、ubuntuをインストール!
こちらもインストール作業は問題なく完了しました。
不安を感じながらも起動させると、ubuntuは普通に起動しています。
ネットワークの設定などを行い、ネット接続もできています。
Linuxの環境をどうするか考えた結果、CentOSをテキストモードでサーバーとして使い、ubuntuを開発環境として使うという方向で使っていきたいと思います。
VMWareServerのほうが機能としてはよさそうな気もするのですが、ある程度使ってみて最終的な判断をしたいと思います。
VirtualPCにLinuxをインストール ― 2010年02月02日 10時58分57秒
XPMODEを入れたのですが、その中身はVirtualPCという仮想ソフトです。
XPMODE自体は特に問題なく動いているのですが、Linuxが動くか試してみることにしました。
今回は、CentOS5.4を入れてみたいと思います。
ただ、ネットで調べてみると、VirtualPCでLinuxを動かすのは簡単ではないようです。
まず、普通にグラフィカルインストールをしようと思ったら、画面が変になってしまいました。
しょうがないので、テキストモードでインストールしたのですが、テキストモードであれば、特に問題なくインストールができ、一応動作はしています。
しかし、Xは使えない状態なので、グラフィック関係の設定を変更する必要があるのかな?
テスト用のサーバーとしてであれば、使うのには問題ないような気はするのですが、デスクトップとして使うには手間がかかりそうです!
開発用に仮想マシンは作成したいと思っているのですが、VirtualPCを使うか、VMWareServerで行くか、他のディストリビューションで動くかどうかも試して結論を出したいと思います。
XPMODE自体は特に問題なく動いているのですが、Linuxが動くか試してみることにしました。
今回は、CentOS5.4を入れてみたいと思います。
ただ、ネットで調べてみると、VirtualPCでLinuxを動かすのは簡単ではないようです。
まず、普通にグラフィカルインストールをしようと思ったら、画面が変になってしまいました。
しょうがないので、テキストモードでインストールしたのですが、テキストモードであれば、特に問題なくインストールができ、一応動作はしています。
しかし、Xは使えない状態なので、グラフィック関係の設定を変更する必要があるのかな?
テスト用のサーバーとしてであれば、使うのには問題ないような気はするのですが、デスクトップとして使うには手間がかかりそうです!
開発用に仮想マシンは作成したいと思っているのですが、VirtualPCを使うか、VMWareServerで行くか、他のディストリビューションで動くかどうかも試して結論を出したいと思います。
Linux入れ替え2 ― 2009年08月12日 08時37分16秒
前回はまったくインストール作業ができませんでしたが、今回インストール用のイメージファイルを再度ダウンロードして、OpenSUSEをインストールしてみました。
今回は、あまり大きな声では言えませんが、職場でダウンロードしてしまいました。
ライティングまですべて職場で行い、帰ってからインストールを行いました。
OpenSUSEの場合、ディスプレーの設定は最初からVaioの解像度を選択できるため、Ubuntuに比べるとインストール後の設定はかなり楽です。
Ubuntuでは、解像度がひくくリポジトリや設定の追加など、面倒なのですが、インストール時に選択するだけでできるのは、ありがたいですね!
最近はLinuxのインストールで戸惑うようなことはほとんどなくなり、SUSEも簡単にインストールは完了しました。
すぐに広いデスクトップが使えるのは、ありがたいですが、Ubuntuに慣れてきている現状からすると、Vistaほどではないにしても、動作は遅いです。
というよりも、Ubuntuがかなり軽くできているということなのでしょうが、Ubuntuに比べると軽快さはあまりありませんでした。
そこで、Fedoraも試してみようと思っていたのですが、動作に関してFedoraもSUSEと同じようにUbuntuと比べると、軽快さには欠けるのではないかと思っています。
考えた結果、Ubuntuに戻すことにしました。
やはりネットブックという、スペックに制約があるマシンを快適に使うには、軽快なOSは必須と考えます。
XPが今もネットブックで使われているのは、その証だと思います。
あっさり方針変更してしまいましたが、やっぱりネットブックではUbuntuですね!
今回は、あまり大きな声では言えませんが、職場でダウンロードしてしまいました。
ライティングまですべて職場で行い、帰ってからインストールを行いました。
OpenSUSEの場合、ディスプレーの設定は最初からVaioの解像度を選択できるため、Ubuntuに比べるとインストール後の設定はかなり楽です。
Ubuntuでは、解像度がひくくリポジトリや設定の追加など、面倒なのですが、インストール時に選択するだけでできるのは、ありがたいですね!
最近はLinuxのインストールで戸惑うようなことはほとんどなくなり、SUSEも簡単にインストールは完了しました。
すぐに広いデスクトップが使えるのは、ありがたいですが、Ubuntuに慣れてきている現状からすると、Vistaほどではないにしても、動作は遅いです。
というよりも、Ubuntuがかなり軽くできているということなのでしょうが、Ubuntuに比べると軽快さはあまりありませんでした。
そこで、Fedoraも試してみようと思っていたのですが、動作に関してFedoraもSUSEと同じようにUbuntuと比べると、軽快さには欠けるのではないかと思っています。
考えた結果、Ubuntuに戻すことにしました。
やはりネットブックという、スペックに制約があるマシンを快適に使うには、軽快なOSは必須と考えます。
XPが今もネットブックで使われているのは、その証だと思います。
あっさり方針変更してしまいましたが、やっぱりネットブックではUbuntuですね!







最近のコメント